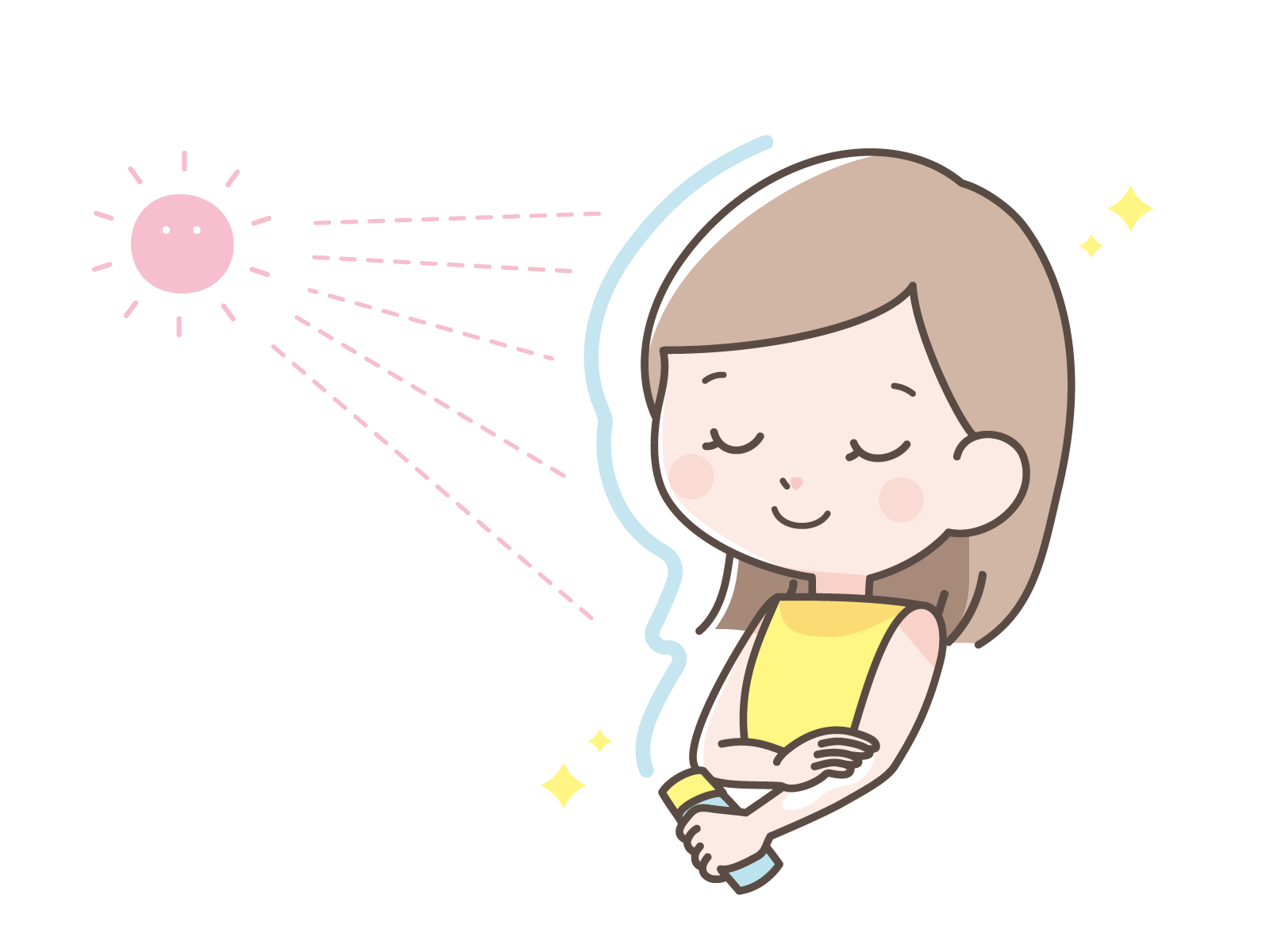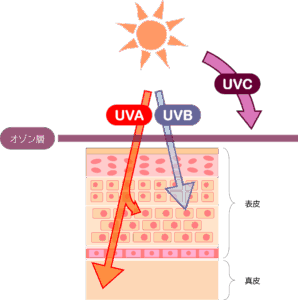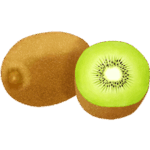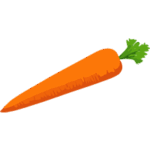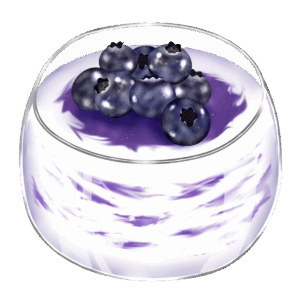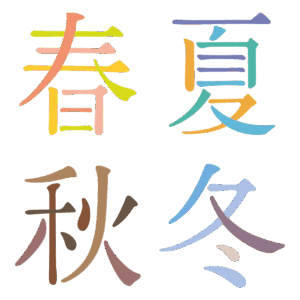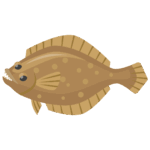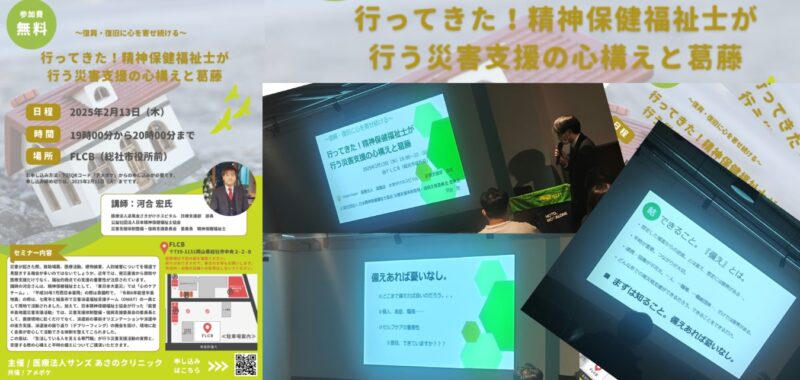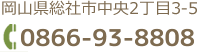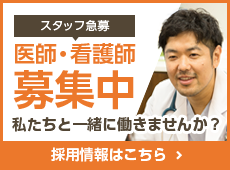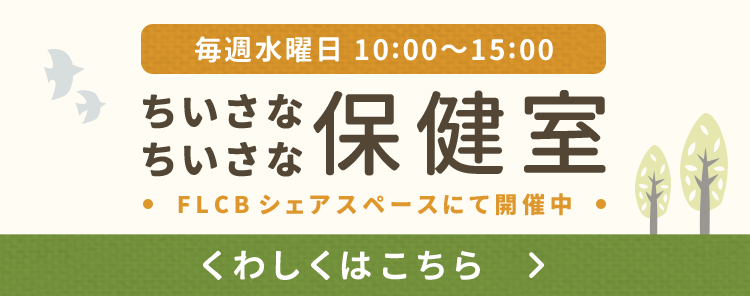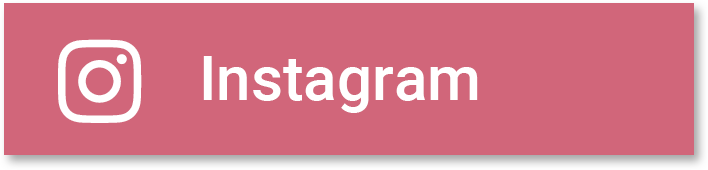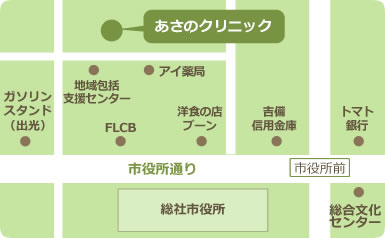あさのクリニック管理栄養士です。
今年の夏は梅雨明けから高い気温が続いていますね。昨年2024年8月の岡山県の平均気温は28.9℃、最高気温の平均は35.7℃、最低気温の平均は27.5℃でした。今年は昨年以上の高温が予想されます。
室内ではエアコンやサーキュレーターを使って温度を調整し、『室内熱中症』を予防しましょう。
年々暑くなっているように感じる日本ですが、世界に目を向けるともっと暑い国がたくさんあります。
日本より暑い国はどうやって暑さをしのいでいるのか見てみましょう!
タイ

タイは一年中蒸し暑い気候ですが、食を通じた暑さ対策の知恵が根付いています。
代表的な料理のひとつに「トムヤムクン」があります。トムヤムクンは、唐辛子の辛味、レモングラスやライムリーフの爽やかな香り、魚介のうま味が合わさった世界3大スープの一つです。食べた瞬間から体が温まり、じわっと汗をかくことで、体内の熱を放出して体温を下げる効果があります。
このようにタイ料理では「スパイスを使って一時的に体温を上げ、汗をかいて冷ます」という、自然なクールダウンの方法がとられています。
また、パクチーやバジルなどのハーブも多様され、消化を助けたり、体内の熱を整えたりする役割を果たしています。香りの強いハーブやスパイスは、食欲が落ちやすい夏にも効果的です。
さらに、ココナッツミルクを使ったグリーンカレーなどは、脂肪の吸収を助けながらエネルギー 補給にもなるため、暑さでバテがちな夏の栄養源としても優れています。
インド

灼熱の太陽が照りつけるインド。昨年インドの首都ニューデリーでは観測史上最高となる52.3℃を記録しました。そんな過酷な暑さのインドでも、スパイスの効能を活かした食文化と乳製品を使って体調を上手に整えています。
インド料理といえば欠かせないのが「カレー」です。ターメリック、クミン、コリアンダー、ジンジャーなど、多くのスパイスがブレンドされ消化促進、抗炎症、抗酸化作用といったさまざまな健康効果が期待できます。
スパイスは体を温めるイメージですが、消化を助け、胃腸の働きを高めることで内側の熱を巡らせて冷ます役割があります。暑さで食欲が落ちやすい夏にこそ、少量のスパイスをうまく取り入れましょう。
また、インドではヨーグルトも日常的に使われています。特に「ラッシー」は暑さで乾きがちな体に潤いを与え、乳酸菌で腸内環境を整えてくれる夏の強い味方です。ほんのり甘くて飲みやすいタイプや、塩味の効いたソルティラッシーなどバリエーションも豊富です。
クウェート、イラク、イラン

クウェートは2016年に54.0℃と非常に高い気温が記録されています。砂漠地帯で、真夏は日中50℃超えも珍しくありません。
イラクは50℃を超える日が続くことも多く、湿度の低い乾燥地帯は日陰でも過酷な気候です。
イランも気温50℃以上を記録することがあり、南部の砂漠地帯は特に暑いです。
そんな中東地域でも、ヨーグルトやラッシーなど発酵乳製品を摂り体の熱を鎮めたり、ペパーミントティーやハーブの冷却効果を活用しています。
さいごに
暑い国々で共通するのは食で整える知恵が生活に根付いていることです。
暑いからといって冷たいものばかり食べるのではなく、敢えて熱いものや辛いものを食べて汗をかく!
夏バテ予防にはこれが1番なのかもしれませんね。
建物の中はクーラーが効きすぎていることが多く、体は意外と冷えてしまっています。
暑い屋外では冷たいものを飲んでも、屋内では温かい飲み物を飲むなど工夫してみましょう。
また、夏野菜は生で食べがちですが、体を冷やす作用があるためラタトゥイユやカレーなど火を通して食べるのもおすすめです。