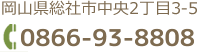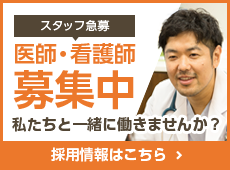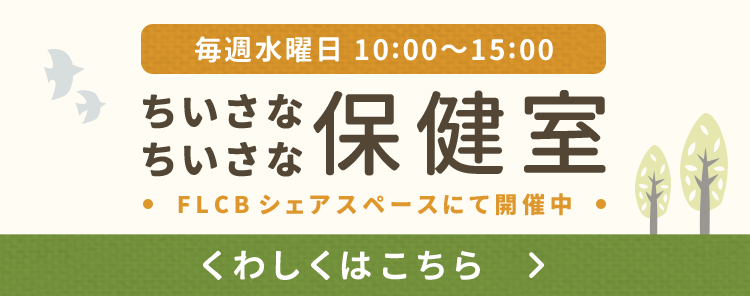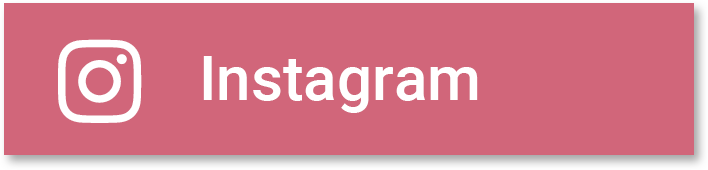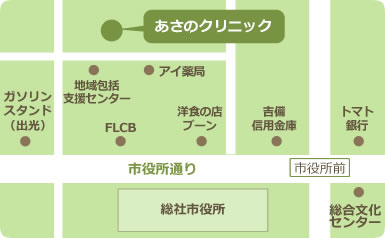権丈ゼミの皆さんから感想をいただきました!その⑥
こんにちは!院長の浅野です。
シリーズ権丈ゼミ 本日がラストです!
いや〜、本当に勉強になりました。学生さんというフレッシュな視点、そして私たちがやっていくべきことの方向性を改めて確認できる良い機会でした。今後ともぜひぜひ交流させていただきたいですね!ありがとうございました!!!
慶應義塾大学商学部 Fさん
***
先日はお忙しい中、クリニックにおいて訪問診療を見学させて頂きまして、誠にありがとうございました。
社会保障についての理論および制度をゼミで学私たちにとって、実際の現場でなされていることを目の当たりに出来たことは非常に大きな経験として今後への糧となると思いました。
私は卒業論文を書くにあたり、社会保障という学問に関して、法学という分野からアプローチを図っています。法学の議論はやはり、現場から乖離せざるを得ない部分があります。今回の見学で「制度は単なる道具であり、それを使いこなすのは現場の人たち」であるという、利用者の権利という視点から見ていく法学からは見落とされがちな「医療・介護を提供する側」の視点というものを深く感じ取ることが出来ました。
浅野院長や、訪問診療でお世話になりました藤原先生、そしてスタッフの皆様を見て、「患者さん、そして患者さんの家族とどう向き合うか」「目の前の患者さんをどう救うか」ということを常に考えて仕事をされていると強く感じました。真に良いサービスを提供するには、仕事と信念を如何に調和させるかだと実感しています。
自分が今後社会に出るにあたってどのような人間像を志向するかということを考える大きなきっかけにもなったと思います。
クリニックの見学を受け入れてくださったことを、重ねまして心より感謝申し上げます。
権丈ゼミの皆さんから感想をいただきました!その⑤
こんにちは!院長の浅野です。
シリーズ 権丈ゼミスペシャル・・・私たちにとって本当に大きな学びとなりました。感謝です!!!
慶應義塾大学商学部 Eさん
***
あさのクリニックの皆さま。短い時間ではありましたが、本当にお世話になりました。とにかく見るものすべてが新鮮で、どこか衝撃的で、自分の中で何か幅が広がっていった気がしました。
今まで「地域包括ケア」として医療の現場を地域・在宅の方向に向けた制度が動いていることは、学校で権丈先生から学び勉強してきました。私は正直、先生が言っているからという理由で、実情はたいして知りもせずに、それはやるべきことで正しいことだからどんどん進めていけばいい、などと思っていました。だから今回、介護サミットなどにも参加した上で初めて現場の側をきちんと見たことで、思っていたほど簡単なことではなく一筋縄ではいかないのだなあというのを肌で感じることになりました。制度設計側と現場との間にも多少の乖離があり、現場の中でも認識・意識の違いがあることを知って、それでも正しい方向に進めていくにはどうしたら良いのかということを考えていかなければならない難しさを改めて感じました。観光は全くできませんでしたが(笑)、本当に岡山まで行って良かったです。見学を快く受け入れてくださり、ありがとうございました。
見学を通して、感じたことはたくさんありました。その中でも自分の中で印象的だったことを文章にさせていただきたいと思います。
最初の退院のカンファレンスにおいては、「病院ではなく家で治療を施す」ということには現実的な難しさがあることを知りました。病院であれば容易にできることが在宅ではそうはいかない、家でできることには制限がある。だから退院後に問題が起きないように退院前にきちんと解消しておかなければならない。退院させさえすればあとは在宅に丸投げ、ではなく、病院と在宅医療との間で適切な役割分担が必要であるということがよく分かりました。
「病院での治療は在宅を見据えたものであるべき」。
在宅で制限がある部分を病院はきちんと補ってあげなければいけません。この点はどの地域においても変わらない部分であり、制度設計の段階でも、誤解のないように後押ししてあげる必要があるのではないかと思います。
次に訪れた訪問診療においては、まず私は、寝たきりでコミュニケーションもほぼ取れないような方をあれだけ間近で見ること自体が初めてで、衝撃を受けました。それと同時に、ここまで重度の方までも家でみるのかと、私たちは地域地域と簡単に言っているけれども将来的にはこうした状態を増やしていくのが現実かと、感じました。「ターミナルケア」では、ご家族のことが特に気にかかりました。完治を目指す治療ではなく緩和治療であるため、困難な状況の末、ご本人やご家族にとって更に辛い症状に苛まれた場合、それが自宅で、目の前で起きたら、介護者はどう思うのでしょうか。
慢性期の患者などに対して、人員不足や医療費削減などのためにも、在宅医療を進めている、この動き自体は間違いではないと思います。特に財源がなく超少子高齢化が進むこの国では仕方のないことだと思います。そして、本人や家族が自宅での療養や最期を望むのであれば問題はないことだと思います。
私がこの構想でイメージしていたのは、家族に囲まれて自宅で幸せに亡くなられるおばあちゃん、といった姿でした。しかし現実を見てみると、イメージ通りとはいきませんでした。広い家の中で、介護者は基本的にずっとベッドサイドにいるのでしょう。ほぼコミュニケーションをとることが出来ない寝たきりの患者さんをずっと看ながら一日中生活していることを想像したら、実際に介護者がどう思ってらっしゃるのかは分からないけれど、もし自分があの状況になったらどんな気持ちになるのだろう…。
外来の見学においては、まず単純に感じたのは、認知症関連で来院する患者さんの多さでした。
来院した方のうち、ご家族と一緒に来られていたアルツハイマー型認知症の方が、個人的には印象的でした。薬を飲んでいる意識がないなど、「忘れてしまっている」ことに対して一瞬見せたあの悲しそうな泣きそうな表情は、忘れられません。自分の家族や近しい人が同じような状態になった時、自分ならどう支えてあげることができるのだろうと、考えるきっかけになりました。
また、外来の患者さんの診察と診察の間に浅野先生にお話いただいたことは、かなり心に残りました。私は、「地域包括ケアといっても、その具体的なやり方は地域に任せる=ご当地」というのはあまりに放任だなあと思っていました。そのやり方が分からないせいで、なかなか実際には進んでいないのではないか、という印象を持っていました。しかし浅野先生の話を聞いて、そういうことではないのだということを強く感じました。上から降ってくる制度が何かしてくれるのを待つのではなく、自分たちがいかに制度を利用するかである。そうしなければ、実情やニーズに合ったものは作れない。目の前の患者さんとどう向き合っていくのか、は制度を待つのではなく、現場にいる人たちが自ら考えていく必要がある。権丈先生が言いたかったことは、丸投げしているのではなく、主体的にやってほしい、ということだったのかなと思いました。そのために今ある社会保障制度をきちんと学んでいく必要があるし、それを最大限活用していくべきです。退院のカンファレンスの後に教えていただいた、訪問看護における介護保険と医療保険の組み合わせの話も、それと似たようなことなのかなと思いました。
見学のあと、現在医学部に通っている小学校からの友人に会いに行きました。そこで、医学部での勉強の話などを聞かせてもらう機会がありました。医療保険をはじめとする社会保障制度や、地域包括ケアについてもきちんと学習していました。私としては、初めてゼミ生以外の同学年の友人と、ゼミで学んだ制度の話を対等にできて貴重な場でした(笑)その子は制度の話は覚える語句の正式名称が長くて嫌いだと言っていましたが、そうした話の中で感じたのは、そうした教育の場においてもっと現実を正しく伝えることが出来たらいいのに、ということでした。特に将来この地域包括ケアの一端を担っていくことになる医者の卵たちが、ただ制度を名前や机上の仕組みだけ覚えるのではなく、病院と在宅との関係性はどうあるべきだとか、現場での実情を知るようになれば、未来はもっと明るいのかなと思いました。
最後にはなりますが、こうした機会を与えていただいて、私は本当に恵まれているなと感じました。最前線で一生懸命に前に進めようとしているのを拝見して、すごく感化されたなと思う部分はやはり大きかったです。私事になりますが、来春より社会人となり、医療介護とは違う方向に進みますが、今後もこうした社会保障制度の中での医療の動きには注目していきたいですし、何らかの形でどこかで今回の経験が生きると良いなあと思っています。少なくとも、現場に、こうやって最前線で頑張っている方がいらっしゃって、地域包括ケアに対して机上の話ではなく進めている現状があるということが分かったこと、そしてそれを生で見ることができたということ、これが自分の中で大きな一歩になったと思っております。本当にお世話になりました。ありがとうございました!
権丈ゼミの皆さんから感想をいただきました!その④
こんにちは!院長の浅野です!!
昨日に引き続き、権丈ゼミの皆さまからのアツい感想・・・行ってみましょう!
慶應義塾大学商学部 Dさん
***
あさのクリニックの皆様
先日はお忙しい中、あさのクリニックのカンファレンスや訪問診療、外来に同行させて頂き、誠にありがとうございました。現場を見せて頂いた事で、文献を調べるだけでは決して得ることのできない体験が出来、とても勉強になりました。
訪問診療に同行させて頂いた際、在宅療養中の寝たきり患者さんとお会いするのは初めてだったのでとても緊張すると同時に、日々患者さんと患者さんご家族と接し、安楽な療養ができるよう尽力していらっしゃる先生方を見て胸に来るものがありました。
ただただ治すだけではない、そういった医療の形があるのだと知ってはいましたが、実際に緩和医療を受けていらっしゃる患者さんと医師を目にする事で、「生きるって何だろう、最期を迎えるって何だろう」と考えました。
それに伴い、浅野先生が患者さん方と接している姿を見学させて頂いて、何よりも大切な事は患者さん、並びに患者さんのご家族の事を第一に気遣い、現状を分かりやすく説明し余計な不安を取り除く事だと感じました。特にカンファレンスでの患者さんへの言葉遣いに気を配っている様子や、認知症の患者さんのご家族と密に今後の治療方針について相談している姿を見て、それこそが理想の医師と患者の関係の姿ではないか、と感じました。
制度という現場とは違う面から勉強している身ではありますが、行政で作られている制度が現場に影響を与える、地続きになっていることを今回の見学で改めて実感しました。私は卒論を「介護保険と障害者政策の普遍化と政策提案」というテーマで執筆する予定ですが、今回の体験を踏まえ、実践的な政策提案ができるよう努めたいと思います。
また、スタッフの皆様にはお忙しい中で送迎をして下さったり、医院の説明をして頂いたりと大変お世話になりました。
重ね重ねになりますが、お忙しい中私共の見学を受け入れて下さり、誠にありがとうございました。
今後、再び権丈ゼミのゼミ生が皆様にお世話になる機会があるかもしれませんが、その時はまたどうぞよろしくお願い致します。
権丈ゼミの皆さんから感想をいただきました!その③
こんにちは!院長の浅野です!!
権丈ゼミの皆さんのアツい感想・・・励みになります!感謝!!
慶應義塾大学商学部 Cさん
***
先日は訪問診療の見学を受け入れて下さり、ありがとうございました。
私のような、医療・介護に関する制度を学び、研究する学生にとって、実際に制度という道具を用い、サービスを提供している現場を見せて頂くことは非常に有益な経験になったと考えております。ありがとうございます。
私なりに、今回の訪問診療見学を通じて大きく二つのことを学ばせて頂きましたので、簡単にですが、以下に感想として記させて頂きます。
先ず一つ目は、国の示す方針と現場とのギャップです。現在、国は医療・介護に関して24時間体制の地域包括ケアネットワークという一つの指針を示しています。このベクトルに沿って現場はサービスを提供するよう求められているわけですが、やはりまだまだ理想の完成形と言える段階ではない。というのも、現場で働く方々が工夫を凝らしながら国の方針に従い業務を行っているものの、経済的、人的な援助が少なく、働く人に負担がかかってしまっているからです。ここに理想と現実のギャップがあると言っても過言ではないと思います。この現実をどう捉えるのか。国の示す方針が本当に正しいのか。何かのアクションが引き金となり解決に向かわないのか、それは何なのか。これらを考えながら政策提言をしなくてはいけない。3時間という短い時間でしたが、多くの課題をついて考える機会となりました。
続いて二つ目は、医師の人としての優しさ、温かさがいかに大切かです。私は藤原先生の訪問診療に同行させて頂いたのですが、先生が患者さん一人一人、またご家族や介護施設の方へも気を配って診療していた様子が非常に印象的でした。もしかすると私と同じ世代の人のなかには、医者は勉強ばかりのどこか冷徹さのある存在に映る方がいらっしゃるかもしれません。これは医学部の受験偏差値が極端に高いことや、近年の医師に対するバッシング、ネガティブな報道の影響かもしれません。しかし、私が総社で目にしたのは温かみがあり、安心して何でも相談できる町のお医者さんでした。親身になって患者さんに対応する、その周りにいる人のケアも忘れない。やがて信頼がうまれ、単なる「医者と患者」以上の人間関係がつくられていく。それが出来るのは勉学における優秀さのみならず、人間的な優しさを兼ね備えた人物のはずです。私はそんな方のこそ医師であってほしいなと今回の見学と通して強く感じました。
以上を私の感想とさせて頂きます。この度は私共の見学を受け入れて下さり、誠にありがとうございました。見学で得た知見を今後の研究活動に活かせたらと存じます。
権丈ゼミの皆さんから感想をいただきました!その②
こんにちは!院長の浅野です!!
昨日に引き続き、権丈ゼミの学生さんからのアツい感想をいただきました。感謝!
慶應義塾大学商学部 Bさん
***
この度は、外来診療を見学させてくださり、ありがとうございました。
最も印象深かったことは、地域の診療所としての役割です。先生が小さいころからお世話になってきたおじいさまを診ることもあり、患者様との距離の近さを感じました。身近な先生の方が、困りごとも伝えやすいですし、先生の側も患者様の性格や生活をよく知っており、的確な助言をできるように思いました。医療行為のみならず、患者様のご趣味を共有して最期の思い出作りを行ったり、ペットやお孫さんについてもお話をされるなど、あらゆるコミュニケーションでもって地域住民を支えていることがわかりました。患者様の健康管理のために定期的に診療の予約をとり、また高度な医療行為は近くの病院へ委託する等、かかりつけ医の役割を果たされているのだと感じました。
もの忘れ外来ではご家族の困りごとや心配事を聞き出し、わかりやすくアドバイスをされていた姿が印象に残りました。認知症の診療では特に、介護者の不安を解消してゆくことが大切なこと、そして正直な相談を引き出すために、先生が患者様と別に、ご家族のみとの対話を重視されていることを理解しました。ご本人との接し方や近所づきあい等についても助言できるのは、認知症サポート医だからこそと思いました。
さらに、医療・介護におけるチーム連携の実際を垣間見ることができました。
診療所内では、相談員の方が事前に患者様の状態を把握して先生に伝えておられ、事前情報のお蔭で、先生がさらに効果的な診療を行えているように映りました。また、先生と相談員や看護師の方が、患者様について話し合って今後の方向性を決められていることも伺い、医療はチームで患者様を支えてゆくお仕事だと実感しました。特に、患者様と向き合う時間を大切にしながら、無理なく勤めてゆくためには、同じ理念を掲げたチーム体制を構築することが不可欠だという先生のお話が印象に残りました。
また、患者様の状態を、医療従事者のみならず介護従事者と共有することを大事にされていることも分かりました。認知症患者の症状を、医療・介護において共通言語化することや、それでもなお先生自身は患者さんの症状を把握するために、診断結果をより詳しく見ていること。また、日常生活支援を受け持つケアマネージャーさんに治療後の注意点を連絡したり、コンピュータを駆使して他職種との連携を取り合っている姿が印象深くありました。
診療所内・外を問わずチーム一丸となって患者様を想い、そして患者様やご家族の方との対話を大切にされている姿を拝見し、地域包括ケアの実際に触れることができました。お忙しい中見学させてくださいました、クリニックの皆様、そして患者様・ご家族の方々、本当にありがとうございました。